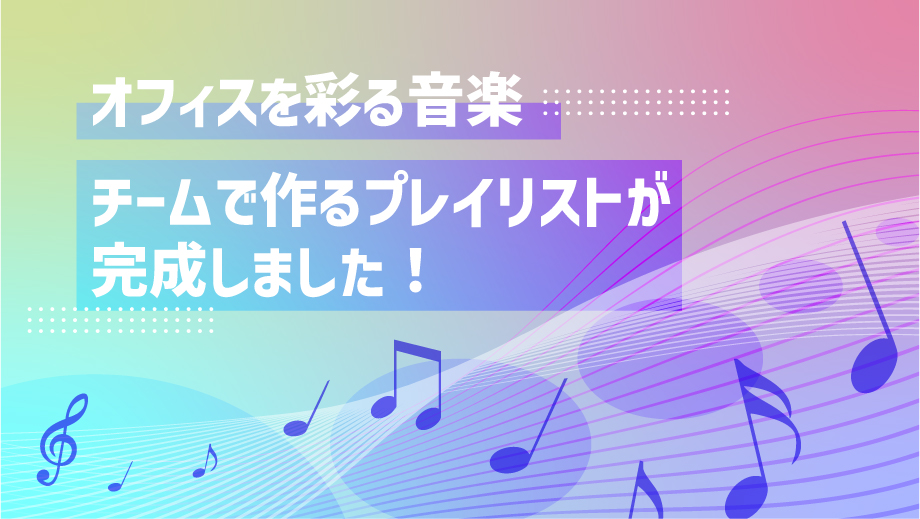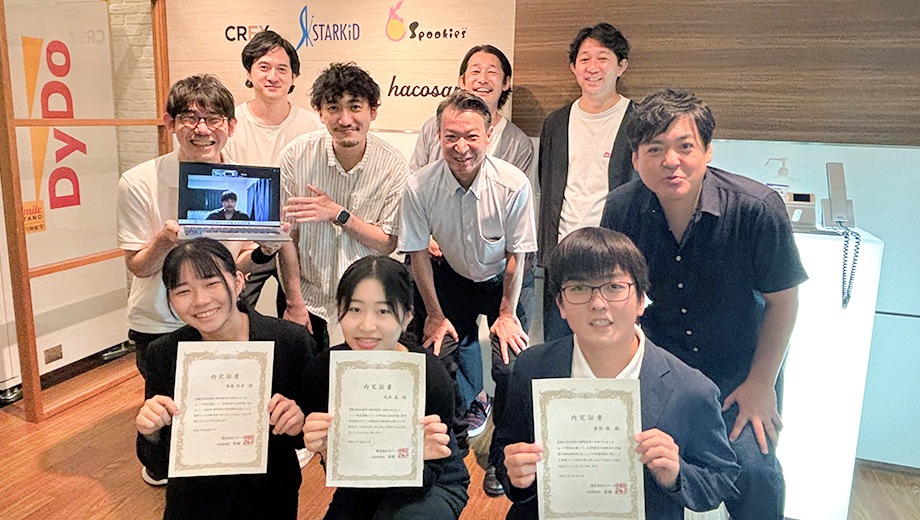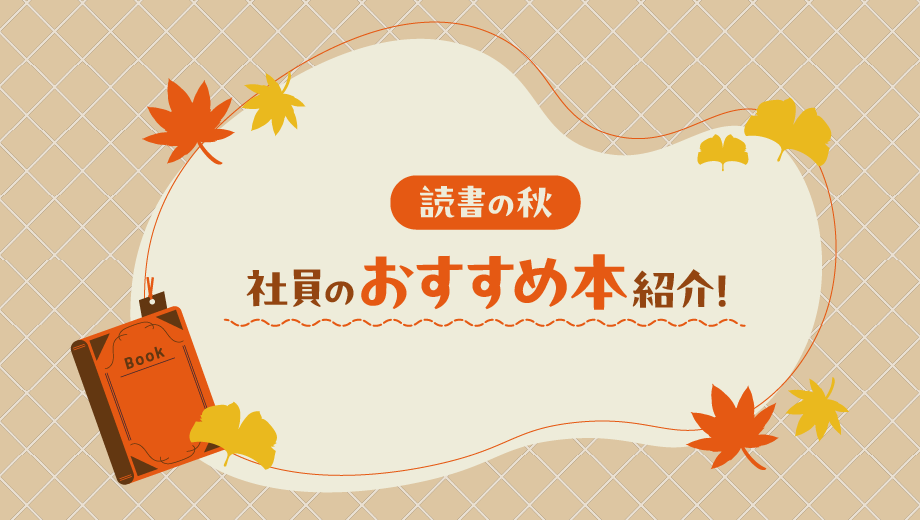2025.10.31
デザインを軸に考える!効果的なWebアクセシビリティ入門

はじめに
現代のWebデザインにおいて、アクセシビリティは重要なテーマの一つです。本記事は、デザインを軸にWebアクセシビリティの基本と優先順位を分かりやすく解説し、効率的な実践方法や、ツールなどをご紹介します。
初めて取り組む方や、さらに深く理解したい方が対象で、アクセシビリティ対応とデザイン性の両立を追求するための道筋を示します。
ウェブアクセシビリティとは何か?
ウェブアクセシビリティとは、障がいの有無や年齢、利用環境にかかわらず、すべての人がWebサイトにアクセスし、情報を得たり操作したりできるようにするための考え方です。これは、視覚障がいのある人向けの音声読み上げソフトへの対応や、マウス操作が困難な人向けのキーボード操作への配慮など、多岐にわたる工夫を含みます。単に技術的な対応に留まらず、すべての人に優しい「思いやりの設計」を目指す姿勢が重要です。
アクセシビリティの重要性とデザインとの両立
アクセシビリティは、視覚や運動機能に制限がある方、高齢者、さらには多様なデバイスや環境に対応するすべての人にとって必要不可欠です。しかしながら、アクセシビリティ対応は必ずしもデザイン性を犠牲にするものではありません。むしろ、人に優しいデザインはスタイリッシュさをも高める可能性があります。
例えば、適切な文字間隔やコントラスト調整は、誰にとっても見やすくなるだけでなく、洗練された印象を与えます。本記事では、デザインとアクセシビリティの調和を重視しつつ、効率よく取り組むための優先事項を整理していきます。
アクセシビリティの基本デザインと優先順位
以下では、デザインの観点からアクセシビリティ対応を行う際の基本ポイントを、優先順位ごとに解説します。
配色とコントラストの調整(高優先度)
高コントラストは、アクセシビリティにおける最も基本的な要素の一つであり、デザインを洗練させるための重要な手法でもあります。
- 推奨コントラスト比: テキストは少なくとも4.5:1、大きいフォントの場合は3:1以上に設定する。
- 配慮ポイント:色覚異常の利用者にも対応できるよう、情報を色で伝えるだけでなく形やテキストでも補足。
- 優先順位:デザイン全体で早い段階から配色バランスを意識的に調整しましょう。
色覚異常の利用者配慮について
日本人男性の約5%(20人に1人)、女性の約0.2%が色覚異常(色覚多様性)を持つとされています。
とくに「赤と緑」「青と紫」「黄と淡いオレンジ」などの区別がつきにくくなるタイプが多いとされています。

確認ツールを使用してチェックを
| Color Oracle | OSレベルで色覚タイプ別の見え方をシミュレーションできる。 |
| Coblis – Color Blindness Simulator | 画像をアップして見え方を確認可能。 |
| Chrome拡張:Spectrum / Funkify | ブラウザ上で直接シミュレーションできる。 |
| Adobe XD / Figmaのプラグイン | デザインツール内で「色覚異常プレビュー」が可能。 |

Figmaプラグインを活用し、制作中からチェックを
Color Palettes ( Colorsinspo ) : Color & Accessibility Tools
読みやすさを高めるタイポグラフィ設計(中優先度)
適切な文字サイズや行間の設定は、デザイン性とアクセシビリティの両方を向上させます。
文字サイズに関する主な基準は、WCAG 2.2 / JIS X 8341-3:2016 の中で以下のように定められています。
| 1.4.4 テキストのサイズ変更(AA) コンテンツまたは機能を損なうことなく、支援技術を使わずに、テキストを最大 200% まで拡大できるようにする。 |
拡大しても崩れないレイアウトにする
- FlexboxやGridを使ってレイアウトを柔軟に
- 高さ・幅を固定値で縛らない
- テキストを画像化しない(代替テキストがあっても読みにくい)
最低文字サイズの目安(ユーザー体験の観点)
ガイドライン上は「最低○px」とは定義されていませんが、実務的には
- 本文:16px前後(1rem)
- 見出し:18〜24px以上
が読みやすさの基準とされています。
絶対値(px)ではなく相対値(em, rem, %)を使う
font-size: 1rem;のように相対指定にすることで、
ユーザーがブラウザの設定で文字サイズを拡大・縮小しても対応できる。
行間・文字間も含めて可読性を確保
- 十分なコントラスト(1.4.3 コントラストの基準)
- 行間: 1.5倍程度を推奨することで視認性を向上
- 簡潔で認識しやすいサンセリフ体やゴシック体を使用。
よく使用されているWebフォント例
ゴシック系
| フォント名 | 提供元 特徴 | よく使われる場面 |
|---|---|---|
| Noto Sans JP | Google Fonts。 無料・多言語対応。視認性が高くどんな端末でも安定。 | 汎用サイト、UI、企業サイト全般 |
| Roboto / Roboto Condensed | Google Fonts。英数字との相性が良い。 | グローバルサイトやテック系 |
| M PLUS 1p / 2p | Google Fonts。軽量で丸みがありやわらかい印象。 | 教育・女性向け・採用ページ |
| 游ゴシック体(Yu Gothic) | Windows / macOS標準搭載。Webフォントでなくても指定しやすい。 | 官公庁・企業系・汎用的 |
| Hiragino Sans / ヒラギノ角ゴ | macOS標準。クオリティ高く、上品。 | ブランドサイト、デザイン重視 |
明朝系
| フォント名 | 提供元 特徴 | よく使われる場面 |
|---|---|---|
| Noto Serif JP | Google Fonts。明朝系の定番、無料。 | コラム、文化系、ブランド系 |
| 游明朝体(Yu Mincho) | Windows / macOS標準。読みやすい。 | コンテンツ中心サイト、紙っぽいデザイン |
| Hiragino Mincho ProN | macOS標準。高級感・読みやすさ。 | 書籍系・伝統系・公式発表など |
| 源ノ明朝 (Source Han Serif) | AdobeとGoogle共同開発。漢字のカバー範囲が広い。 | 多言語対応サイト、新聞調の雰囲気 |
丸ゴ系・デザインフォント
| フォント名 | 提供元 特徴 | よく使われる場面 |
|---|---|---|
| Rounded M+ | GM PLUSの派生で、角丸。かわいくて親しみやすい。 | 女性向け・採用・教育 |
| Kosugi Maru | Google Fonts。軽量でUIにも使いやすい。 | カジュアル系サイト |
| BIZ UDPゴシック/明朝 | IPAフォントの後継。ビジネス文書に強い。 | 官公庁・企業内システム |
画像や動画の使い方(中優先度)
ビジュアル要素を活用しながらも、すべてのユーザーに配慮した使い方を心掛けます。
- 代替テキスト:画像には適切な”alt”属性を設定。
- 動画:自動再生を避けるほか、再生コントロールを提供する。
- 優先順位:意味を持つ画像や動画から対応を進める。
レイアウトと構造(高優先度)
論理的で直感的なレイアウトは、情報の整理やスムーズな操作を実現します。
- 見出し:h1からh6まで正しい階層で整理。
- ナビゲーション:パンくずリストや適切なリンク構造で道筋を明確化。
- フォーム:入力フィールドには適切なラベルを設定。
アクセシビリティ対応の実践:チェックリスト
すぐに実践できるポイントを、優先順位に沿って以下に示します。
- 配色のチェック(高優先度)
テキストと背景のコントラスト比が基準を満たしているか確認。 - レイアウトの整備(高優先度)
情報の整理が直感的に行われているか。 - タイポグラフィ(中優先度)
文字サイズや行間が適切で読みやすくなっているか。 - 画像や動画(中優先度)
すべての画像に代替テキストが設定されているか。 - キーボード操作
キーボードだけで操作が完結するよう作られているか。
チームで取り組むアクセシビリティ

アクセシビリティ対応は、デザイナーだけでなくチーム全体での取り組みとして進める必要があります。
- 教育と共有
チーム全員でアクセシビリティの基礎を学び、考えを共有する。 - 内部方針の統一
社内ルールやチェックリストを作成して改善を進める。 - ツールの活用
Google Lighthouseやaxe DevToolsなどを使用して課題を検出。
デザインとアクセシビリティが両立する未来へ
洗練されたデザインとアクセシビリティの両立が、すべてのユーザーに豊かな体験を提供します。改善の第一歩は、ほんの小さな調整からでも始められます。美しいデザインとアクセシブルな機能を追求する中で、ユーザーにとって本当に価値のあるWeb体験を目指しましょう。
まとめ
- WEBアクセシビリティの基本理念:
障がいや環境に関わらず、すべての人がWebサイトを利用可能にする「思いやりの設計」であり、デザイン性とも両立する。 - 【高優先度】デザイン対応:
コントラスト比を基準(例: 4.5:1)で確保し、色覚異常にも配慮する。
レイアウトと構造は、見出しタグ(h1〜h6)で論理的に正しく整理する。 - 【中優先度】デザイン対応:
タイポグラフィは、本文16pxを目安に相対値(remなど)で指定し、読みやすい行間を設ける。画像には必ず意味を伝える代替テキスト(alt)を設定する。 - 実践・体制:
サイト全体がキーボード操作だけで完結することを確認する。
アクセシビリティはチーム全体で取り組み、ツールなどを用いて継続的に改善する。
WEBアクセシビリティの実装ポイントを知りたい方はこちら
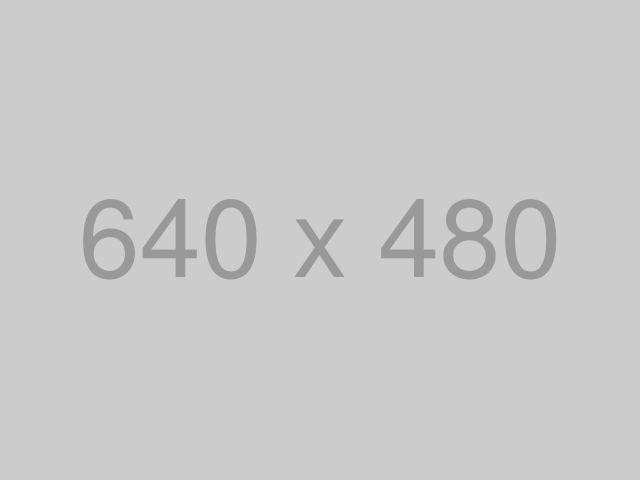
いいねありがとうございます!